蝉の声が聞こえ始め、夏の訪れを感じるこの季節に、あなたは今、きっと特別な想いで「お盆」の準備を進めているんじゃないかな。
特に、大切な方が旅立たれてから初めて迎える「新盆(しんぼん)」は、いつもとは違う、静かで、でも温かい気持ちが心に満ちるよね。
「今年は、いつものお参り以上に、心を込めてご先祖様に感謝を伝えたいな…」
「ありがとうって気持ち、どうしたらちゃんと届くんだろう…」
そんな風に思った時、「祝詞(のりと)」という言葉が頭に浮かぶかもしれないね。
でも、なんだか神主さんが唱えるような、難しくて、自分には縁遠いものに感じてしまったり…。
大丈夫。その優しい気持ちがあれば、何も心配いらないよ。
この記事では、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えるための、もう一つの素敵な言葉「拝詞(はいし)」について、誰でも今日から実践できる、やさしい方法を紹介していくね。
難しいルールは一旦忘れて、あなたらしい言葉でご先祖様と語り合う、温かいお盆の過ごし方を、一緒に見つけていこう。

「祝詞」と「拝詞」ってどう違うの?お盆に最適なのはどっち?
まず、ちょっとした言葉の豆知識から。
「祝詞」と「拝詞」、似ているようで、実は少しだけニュアンスが違うんだ。
すっごく簡単に言うと、お手紙の「宛名」が違うようなもの。
「祝詞(のりと)」は、主に神社の神様へお伝えする言葉。
「拝詞(はいし)」は、神様はもちろん、ご先祖様(祖霊様)への感謝や祈りを伝える時にも使われる、より広い意味を持つ言葉なんだ。
だから、お盆にご先祖様への感謝を伝えたい、という場面では「拝詞」という言葉の方がしっくりくるかもしれないね。
でも、一番大切なのは呼び方じゃないんだ。
祝詞も拝詞も、その根っこにあるのは「目には見えない尊い存在への、敬いと感謝の心」。
どっちの言葉を使っても、あなたのその純粋な気持ちが、一番のご馳走になるから、安心してね。
そもそも、なぜ7月にお盆があるの?(豆知識)
「あれ、お盆って8月じゃないの?」
そう思っている人も、きっと多いよね。実際に、全国的には8月15日を中心にお盆を行う地域がほとんど。
じゃあ、なんで7月にお盆があるんだろう?
これは、日本の暦(こよみ)が変わったことと関係があるんだ。
昔の日本では、今の暦(新暦)ではなく、月の満ち欠けを基準にした「旧暦」が使われていたんだよ。
旧暦の7月15日は、だいたい今の8月中旬頃にあたる。
明治時代になって、政府が「これからは新暦を使いますよー!」と決めた時、お盆の時期の対応が地域によって分かれたんだ。
「暦が変わったなら、お盆も新暦の7月15日にやろう!」としたのが、東京などの都市部。
だから、7月のお盆は「新暦盆」とか、初めて迎えるお盆と同じ読み方の「新盆(しんぼん、にいぼん)」って呼ばれるようになったんだよ。
あなたが7月にお盆を迎えるのは、昔からの伝統を、暦が新しくなっても大切に受け継いできた証。なんだか、ちょっと素敵じゃない?

【シーン別】そのまま使える!7月のお盆(新盆)の拝詞 例文集
「気持ちは伝わったけど、やっぱり具体的な言葉が知りたい!」
うんうん、そうだよね。最初は例文があると、すごく安心するはず。
ここでは、お盆の代表的な3つのシーンで、そのまま使える拝詞を紹介するね。
まずは、これをそっと心の中で唱えることから始めてみよう。
ご先祖様をお迎えするときの拝詞(迎え火で)
お盆の入り口。夕暮れ時に、玄関先で迎え火を焚きながら、「おかえりなさい」の気持ちを込めて唱える拝詞だよ。
「〇〇家(〇〇け)の御先祖様(みおやさま)、ならびに新仏様(あらみたまさま)。
お盆を迎え、謹んでお迎え申し上げます。
短い間でございますが、どうぞごゆっくりお過ごしください。
かしこみ、かしこみ、白す(もうす)」
「我が家のご先祖様、そして今年初めてお盆を迎える〇〇さん。お帰りなさい。どうぞ、ゆっくりしていってくださいね」という、温かいお迎えの言葉だよ。
お盆の間、日々唱える感謝の拝詞(御霊舎・仏壇の前で)
お盆の間、朝起きた時や、ご飯をお供えする時などに、御霊舎(みたまや)や仏壇の前で手を合わせて唱える拝詞。日々の感謝を伝える言葉だね。
「〇〇家の御先祖様。
日々の御守護(ごしゅご)、誠にありがとうございます。
本日も、家族一同、息災に過ごしております。
どうぞ、安らかにお鎮まりください。
かしこみ、かしこみ、白す(もうす)」
「ご先祖様、いつも私たちを守ってくださって、本当にありがとうございます。おかげさまで、今日も家族みんな元気に過ごしています。どうぞ、安らかにお過ごしくださいね」という意味。毎日の「ありがとう」を伝える、大切な習慣だよ。
ご先祖様をお送りするときの拝詞(送り火で)
お盆の終わり。送り火を焚きながら、「また来年、元気で会いましょう」という気持ちと、これからの家族の安全を願う、お見送りの拝詞だよ。
「〇〇家の御先祖様。
楽しいお盆の時も過ぎ、お送りの時となりました。
名残惜しゅうございますが、どうぞお帰りください。
これからも、私ども家族をお見守りください。
かしこみ、かしこみ、白す(もうす)」
「ご先祖様、楽しい時間はあっという間でしたね。お見送りするのは寂しいですが、どうぞお気をつけてお帰りください。そして、これからも私たちのことを見守っていてくださいね」という、感謝と祈りを込めたお別れの挨拶なんだ。

世界に一つだけ。あなただけの「感謝の拝詞」書き方3ステップ
例文を唱えるだけでも、あなたの気持ちはきっと届く。
でも、もし「もっと自分の言葉で、あの人への想いを伝えたいな」って感じたら、それは、あなただけの特別な拝詞を作る最高のチャンスだよ。
難しく考えなくて大丈夫。たった3つのステップで、誰でも作れるからね。
ステップ1:「ありがとう」を書き出してみよう
まずは、ペンと紙を用意して。
そして、あなたが感謝を伝えたいご先祖様、特に新盆で迎える大切な故人のことを、ゆっくり思い出してみて。
- どんな笑顔が好きだった?
- どんな言葉をかけてくれた?
- 一緒に過ごした、一番の思い出は?
- その方から受け継いだ、あなたにとっての宝物はなに?
- 今、一番「ありがとう」と伝えたいことは?
思いつくままに、言葉を書き出してみてね。それが、あなたの拝詞の「核」になるから。
ステップ2:3つのパーツで組み立てる
次に、書き出した言葉を、簡単な3つのパーツに分けて組み立ててみよう。
- 呼びかけ:「拝み奉る(おろがみまつる)、〇〇(故人の名前)の御霊(みたま)」のように、誰に伝えたいかを明確にするよ。
- 感謝の言葉:ステップ1で書き出した「ありがとう」を、自分の言葉で繋げてみよう。「あなたの優しい笑顔は、いつも私達を照らしてくれました。たくさんの愛情を、ありがとうございました」みたいにね。
- 結びの祈り:「これからも私達家族を、安らかにお見守りください」など、未来への祈りで締めくくるよ。
この3つのパーツを繋げるだけで、もう立派なオリジナル拝詞の骨組みが完成だね。
ステップ3:丁寧な言葉で整える
最後に、ちょっとだけ丁寧な「魔法の言葉」を加えて、全体を整えてみよう。これを使うと、ぐっと拝詞らしくなるよ。
- ~給い(たまい):「お守りください」を「守り給い」と言うように、言葉を柔らかく、敬意を込めた表現にする言葉。
- かしこみかしこみ白す(もうす):「謹んで申し上げます」という意味の、とても丁寧な結びの言葉。これを最後に加えるだけで、全体が引き締まるよ。
例えば、「あなたの笑顔、忘れないよ。ありがとう。これからも見守っててね」という気持ちが、「御霊の優しい笑顔を忘れず、心より感謝申し上げます。これからも私達を、見守り給えと、かしこみかしこみ白す」みたいに、グッと素敵な拝詞になるんだ。
さいごに
どうだったかな?
お盆に唱える拝詞で一番大切なのは、上手な言葉や難しい形式じゃなくて、あなたの「心からの感謝」の気持ちだっていうこと、感じてくれたら嬉しいな。
たどたどしくても、あなたの本当の気持ちがこもった言葉こそ、ご先祖様にとっては何より嬉しい、最高の贈り物になるはずだから。
この夏、あなたらしい言葉で、ご先祖様とゆっくり対話する時間を過ごしてみてね。
きっと、いつもより温かくて、豊かで、心に残るお盆になるはずだよ。

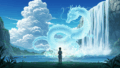

コメント